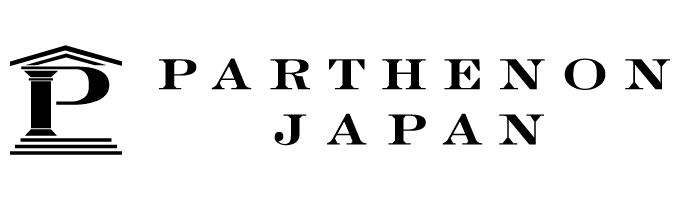日本活性化(パート1):エネルギー自給の実現のために地方が果たす役割とは
エネルギー自給は多くの国々の課題であり、特に地政学的・資源的な制約が加わった現在、より一層重要視されている。日本は国外の資源に依存しているため、おそらく今後もエネルギーの純輸入国であり続けるだろう。他方、風力発電や太陽光発電、バイオマスエネルギー、原子力発電の技術向上により、日本ではエネルギーの多様化が進んでいる。水力発電・地熱発電・核融合発電は、従来の石油・天然ガス・石炭に代わる有望な代替エネルギーとして検討されている。しかし日本は現実的にどうすれば代替エネルギーを得てエネルギーの自給を実現できるのだろうか。
いくつかの選択肢を検討してみよう。
エネルギー自給の鍵を握るのは、すでに未来のためのエネルギー革新を先導している日本の地方だろう。地方では、日本の国外資源への依存度を下げるために、新技術を用いた活気に満ちたプロジェクトが進められているが、しかしこれには時間を要するだろう。
エネルギー革新は日本の地方に恩恵をもたらす一方、エネルギー資源を国外からの輸入に依存している現状において、地方はリスクにさらされている。農業や製造業などの主要産業は電力を必要とするため、電力価格が高騰するほど、収益性の高いビジネスを行うことは難しくなる。
まず現状を把握しよう。経済産業省資源エネルギー庁によると、2019年度の日本のエネルギー自給率はわずか12.1%だった。日本が充分なエネルギー自給率を達成するためには、過去にそうしてきたように引き続き改革を進める必要があることは明らかであるし、エネルギー自給に向けて毎年前進している。2021年には、日本のエネルギーの16%を太陽光、11%を水力、5%を風力、5%をバイオマス、1%を地熱が占めるようになった。
充分なエネルギー自給の達成にはまだ何年も要するが、日本は変化を受容することに長けた国だ。明治維新(1868年〜1912年)はその好例である。指導者たちは日本が西洋との競争力に欠けることを認識し、西洋のやり方を研究して必要な原理原則を自国に適用することを強く推し進めた。このことは、自国の技術革新と組み合わさることで力強く作用し、産業と社会の急速な変化につながった。
明治時代以前でも、岩手県釜石市は鉄鋼生産王国への道を進んだ。1857年、日本初のヨーロッパ式高炉を建設した釜石は、地域のリーダーとしての役割を果たしていた。このような先進性は、現在も日本各地で見ることができる。
こちらの記事は、「地方創生」をテーマにしたシリーズの第1回目です(全6回)。本記事と合わせて、パルテノンジャパンの新しい公式ポッドキャスト「Japan Unleashed」でも、各トピックを取り上げています。(英語のみ)
エネルギートランスフォメーション
近代化が進んだ明治時代には、江戸時代400年間、3000万人前後で安定していた人口が急激に増加した。しかし、増加し続けるエネルギー需要に国内資源が追いつかず、自給率は低下せざるを得なかった。
人口減少が進む今、エネルギーの自給は可能なのだろうか。ここで、近代日本のエネルギーの変遷における重要なポイントを簡単に振り返ってみたい。
日本は、産業や軍事、消費者の需要を満たすために、国内の石炭と天然ガスに大きく依存してきた。そして、石炭に代わるエネルギーとして石油が普及した。国産エネルギーの探索が進み、1915年、秋田県の秋田・黒川油田で大規模な地下資源が掘り起こされた時、油田開発はその生産量のピークに達した。しかし、第一次世界大戦が勃発し開発機材の輸入が途絶えると、新たな油田開発は停滞し、国内の生産量は減少に転じた。それ以来、国内の石油生産量は下降線をたどっている。第二次世界大戦勃発直前、日本は石油の90%以上を輸入に依存していたため、枢軸国として連合国の主要産油国から禁輸措置を受けたことは、日本が戦争を始めるきっかけの一つとなった。
戦後日本の経済成長は更なる電力需要の増加を招き、自給率は年々減少していった。1960年に58%だった自給率は、2014年には過去最低の6.4%を記録した。日本が再生可能エネルギーを本格的に導入することは、単にCO2削減論者をなだめるだけではなく、経済的な安定と競争力を維持するための唯一の手段なのである。
エネルギーに関する取り組み
現在日本は国の施策により、将来のために効果的なエネルギーミックスの実現に向けた取り組みが進んでいる。日本のエネルギー政策は、「S+3E(安全性+安定供給、経済効率性、環境適合)」の原則のもと、規制緩和にフォーカスした多層的なエネルギー供給構造となっており、各エネルギー源が最適に機能することを目指している。
上記の取り組みに加えて、福島第一原発事故を契機に災害への対処のための企業間連携の強化、災害に強い送配電系統の構築、分散型電力システムの導入など、国を挙げてのエネルギーキャンペーンが展開されている。再生可能エネルギーを統合するための送配電系統の再構築や、コスト負担の在り方に関する議論が国レベルで進められているが、地方レベルではどうなのだろうか。
地方の取り組み
福島第一原発の事故を契機に、日本各地の自治体では、「再生可能エネルギー協議会」などの再生可能エネルギーネットワークが共同で設立されている。さらに、協同組合や市民団体、地域の再生可能エネルギー発電事業者やその他の研究機関などが積極的に情報発信を行うようになっている。
日本の電力市場は2016年に電力小売事業の新規参入を開放し、エネルギーの直接供給に特化した地元企業の設立を自治体に促した。その結果、電力供給の統制の強化・電力料金の値下げという成果が得られた。また、近年地域的なプログラムも受け入れられてきた。日本気候イニシアティブ(JCI)は、100を超える日本の企業・地方自治体・研究機関・NGOによって設立され、コミュニケーションを強化するとともに、日本における気候目標の達成のために考案された戦略の共有をしている。
さらに、地方自治体は世界的な取り組みであるCOP27目標に参加し、全国的な炭素クレジット制度を通じて排出量を制限するための取り組みを行っている。このような背景から、国内外のプレーヤーが日本のエネルギー市場に参入し、炭素クレジットを販売する機会が生じている。
ここでは、注目すべき地方の取り組み事例を見ていく。
- 神奈川県は太陽光発電設備の共同購入により費用対効果の高い太陽光発電の導入を進めている
- 横浜市と東北地方の12自治体は2019年に連携協定を締結。横浜市内の中小企業に対し、東北の再生可能エネルギー発電所で発電した電力を購入するよう促している
多くの自治体が長期的なエネルギー目標に取り組んでいる。
- 200以上の自治体(人口総合計、9000万人以上)が、ゼロ・カーボン都市を目指すことを表明している
- 長野県は、東京都と協力して、地域内の建物における太陽光発電の可能性を把握するためのソーラーマッピング・プロジェクトを開始した
このような取り組みが、日本の再生可能エネルギー普及を後押ししている。電力需要が大きい大都市圏の自治体は、再生可能エネルギーの供給に課題を抱えており、地方の自治体との連携が、カーボンニュートラルの実現を大きく後押ししている。
再生可能エネルギーの懸念点
日本のエネルギーミックスは急激に多様化しているが、再生可能エネルギーにマイナス面や課題がないわけではない。
2011年の福島第一原発の炉心溶融は、地震・津波の被害が想定される地域に原子力発電所を建設したことが直接の原因であるために、原子力エネルギーに対する国民の信頼を大きく損なった。日本は震災直後にすべての原子力発電所を停止させ、2015年までにわずか2.5%の発電所のみが再稼働した。再稼働のたびに地元住民の反対運動が生じている。原発に対する世論は圧倒的に否定的であり、日本における原子力の将来は不透明である。
太陽光発電は再生可能エネルギーの代表格としてよく挙げられるが、発電効率の向上や生産コストの削減が進んでも、欠点がないわけではない。日本では福島第一原発事故後、太陽光発電の更なる導入拡大を願い、政府が民間から極端な好条件で太陽光発電の買取を進めた。そのためゴールドラッシュのように、国内外の企業がこの制度を利用し太陽光発電所の開発を急進する動向が見られた。その結果、大規模な太陽光発電プロジェクトが勃興したが、その多くは管理が不十分で、地方の安い丘陵地帯に建設された。太陽光発電所に関する規制の欠如は、大規模な土砂崩れを招き、地元住民による大規模太陽光発電所への反対運動を引き起こした。
その他の再生可能エネルギーにもデメリットがないわけではない。風力発電は定期的なメンテナンスが必要だし、地域社会からは景観を損なうという声も挙がっている。日本は豊富な地熱資源を有するが、効率的な利用のために必要な湯量と高温を確保できる地域は限られている。またそのほとんどが当然のことながら温泉地である。地熱発電は温泉の温度や質を変えるという噂もあり、地元の宿泊施設の経営者や関係者は、地元での地熱発電に激しく反対している。
将来的な目標
欠点はあるにせよ、再生可能エネルギーが日本のエネルギー問題を解決する鍵であることは明らかだ。データセンターやその他の電力集約型施設の数の増加により電力需要はさらに増加している。だが、日本の現在のエネルギー送配電系統は、それに対応する長期的な発電能力に欠けている。送配電系統と蓄電の容量には限りがあるものの、水陸両方で蓄電能力の向上が見込まれている。仮に蓄電能力の向上が達成されたとしても、依然として課題は残る。
エネルギーの再活性化を加速するために必要なことは何か。私たちのアイディアを以下に挙げる。
- 再生可能エネルギー事業に対する地方と国の支出を増やす。例えば、メイド・イン・ジャパンの蓄電池や効率的な太陽光発電技術のための研究開発資金を支援する
- 固定価格買取制度(FIT)を改善する。これにより、住宅所有者、事業主、農家、個人投資家は、送配電系統に供給する再生可能エネルギー電力のための基本コストの負担能力を拡大するだろう。加えて、多様な再生可能資源の開発を促進し、投資家に投資収益を提供するだろう
- 大都市圏と小規模な送配電系統事業者の間の需給連結を構築・強化するための取り組みを継続する
- 民間部門の取り組みをさらに統合し、再生可能エネルギーへの追加投資を刺激する
再生可能エネルギーへの取り組み
日本政府は、再生可能エネルギーを推進し、地方の反発を抑えるルールや制度、ガイドラインの整備を進めていくだろう。しかし、再生可能エネルギーの未来はどこへ向かっているのだろうか。
再生可能エネルギーに関する様々な取り組みが行われているが、残念ながら国民からの賛同は得られていない。
- 東京都の小池知事は、2025年度までに新築の住宅や集合住宅に太陽光発電パネルの設置を義務付けると発表した。家庭部門からの二酸化炭素排出量を削減するため、2022年12月に東京都議会で承認されたものである。東京都は、2030年までに二酸化炭素の排出量を2000年比で半減させることを目標としている。これは東京都が断行した決定であるが、都民との充分な対話がなされておらず、理想的なものとは言えない。
- 埼玉県比企郡小川町に民間企業が計画している大規模太陽光発電所の建設は、さらなる改革の必要性を浮き彫りにした。自然の美しさを求めて移住してきた人々が多く住む地域に、大規模な太陽光発電所を建設するには、政府による監督と住民との対話が必要だ。この2つの要素の欠如は地元住民の強い反対を招いた。透明性を確保し、持続可能な開発のためのルールを作ることが、地域社会との信頼関係を築く唯一の方法である。
信頼が非常に重要だ。準備不足により招かれた福島第一原発の痛ましい事故は、未だ人々の記憶に新しい。科学に対する国民の信頼の失墜は、今日でも続いている。しかし一方、エネルギー自給率の向上を短期間で実現するためには、日本の原子力発電所を再稼働させる必要がある。日本の原子力発電は福島第一原発事故以前、総電力の約30%を供給していた。2022年6月現在、国内の54基の原子力発電所のうち、地元の許可を得て再稼働しているのは10基のみである。
福島第一原発事故以来、大規模原子力発電に対する日本国民の信頼は回復していない。また、原子炉は老朽化が進んでいる。従って、日本はより少ない設置面積、高い安全性・効率性が約束された新しいタイプの原発への投資に重点を移すことになるだろう。明確で正直なコミュニケーションこそが、国民の信頼を回復する唯一の方法である。
将来への展望
長期的には、再生可能エネルギーの生産コストは、規模が大きくなるにつれて低下するだろう。これは、運転資金や投資インセンティブの不足に悩む地方にとって朗報となるだろう。また、現在送配電系統から外れている地方のシステムでも、地元にある資源を利用して直接発電し、地方に供給することができるようになる。これは、地域経済の活性化や競争激化による電力料金の引き下げに貢献する。
技術的な取り組みと政策的な取り組みが組み合わさった、持続可能なビジネスモデルをさらに発展させることが、再生可能エネルギーに着目したエネルギーミックスをさらに成長させる鍵となる。地方における取り組みは、日本がエネルギーの自給を目指す上で核となる活動である。
その実現には国を挙げての取り組みが必要であり、国と地方のステークホルダーとの効果的なコミュニケーションが大変重要だ。エネルギー自給の重要性を国民が理解し、政府の取り組みに対し信頼と自信を持つことによってはじめて、日本は課題を克服し、持続可能な経済の安定へと向かうこの重要な取り組みを達成することができる。
文: パーカー・アレン、デビッド・ワグナー
パーカー・アレンはパルテノンジャパンの代表取締役社長を務める。デビッド・ワグナーはパルテノンジャパンの上席顧問であり、メディアトレーニング・クライシスコミュニケーションの分野を担当。